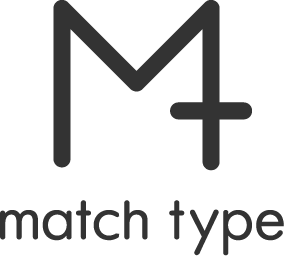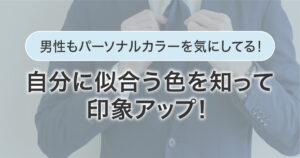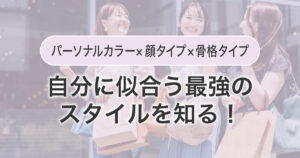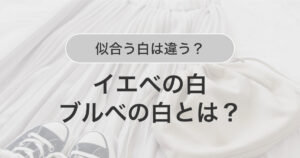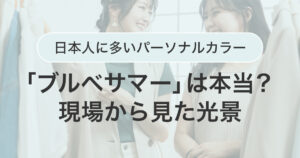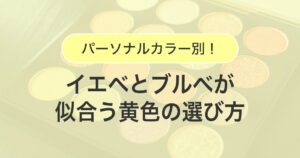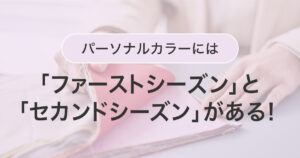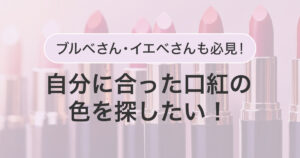パーソナルカラーは、「似合う色」を科学的に分析する理論として発展し、美容やファッション業界で広く使われています。
流行りだしたのがここ数年なので、パーソナルカラーが出来たのは最近だと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はかなり昔から知られている理論です。
その起源は、美術や色彩学に基づく考え方にあります。
この記事では、パーソナルカラーの発展の歴史について深掘りしていきます!
ルネサンス時代と色彩理論の始まり

パーソナルカラーの基盤は、ルネサンス時代の美術研究にさかのぼります。
この時期、光と色の関係性に注目した研究が進みました。
レオナルド・ダ・ヴィンチは、影や光の作用が色彩に与える影響を観察し、作品に活用しました。
17世紀には、アイザック・ニュートンがプリズムを用いて白色光を分解し、光のスペクトルを発見しました。
これにより、色が光の物理的な性質に基づいていることが科学的に証明され、後の色彩理論の基礎となります。
18~19世紀:色彩調和論の発展


18世紀には、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが『色彩論』を著し、色が人間の感情や心理に与える影響を探究しました。
ゲーテの『色彩論』は、前述のニュートンが提唱する考え方を真っ向から否定するものであったため、ニュートンの考え方が浸透していた当初はゲーテの『色彩論』はあまり評価されませんでした。
しかし後に、ゲーテの『色彩論』はこころの動きを研究する「心理学」に近く、現代で言う「色彩心理学」の先駆けとなった研究だと考えられるようになっています。
『色彩論』は、科学的色彩理論とは異なる人間的な視点で色を捉えたもので、美術やデザインの世界に大きな影響を与えました。
19世紀に入ると、ミシェル・シュヴルールが「同時対比の法則」を提唱し、色の組み合わせによって視覚的な効果が変化することを説明しました。
この考えは「色彩調和論」として知られ、現在のパーソナルカラー理論にもつながる重要な概念となっています。
20世紀前半:シーズンカラー理論の誕生
1920年代、スイスの芸術家であり色彩研究家でもあるヨハネス・イッテンが、色彩学に基づく「色の7つのコントラスト」を提唱しました。
彼は色の属性(明度、彩度、色相)が人々の肌や髪、瞳に与える影響に注目し、美術教育に応用しました。
イッテンの理論は、後に「春夏秋冬」の4つのシーズンに基づくパーソナルカラー理論の基盤となっています。
20世紀後半:パーソナルカラー理論の確立

1970年代、アメリカの色彩コンサルタントであるキャロル・ジャクソンが、著書『カラー・ミー・ビューティフル』で4シーズン分類のパーソナルカラー診断を提唱しました。
この方法は、肌の色、髪の色、瞳の色に基づいて「春・夏・秋・冬」のどれかのシーズンに分類し、それぞれに適した色を提案するものでした。
この理論は、ファッション業界や美容業界で瞬く間に広まり、現在のパーソナルカラー診断の基本形となっています。ジャクソンの理論は、各シーズンの特徴を明確に定義したことで、多くの人が自分に似合う色を簡単に理解できるようになりました。
パーソナルカラーと大統領のネクタイ選び:ニクソン大統領とケネディ大統領の例
パーソナルカラーの理論は、政治の場においても効果的に活用されています。
特に、リーダーたちが身につけるネクタイは、メッセージ性や印象操作において重要な役割を果たします。
アメリカの歴史的な大統領討論会である1960年のニクソン大統領とケネディ大統領の討論会では、ネクタイの選び方が大きな話題となりました。
このエピソードは、パーソナルカラーが人に与える印象にどれほど影響を与えるかを示す象徴的な出来事として知られています。
ニクソン大統領とケネディ大統領:対照的なスタイル


1960年の討論会は、アメリカ初のテレビ中継された大統領候補の討論会でした。
このテレビ討論会は、視覚的な印象が選挙戦略においていかに重要であるかを世に知らしめた場でもあります。
ニクソン大統領
リチャード・ニクソン大統領は、この討論会で薄いグレーのスーツと淡いネクタイを選びました。
しかし、この選択が彼の印象に悪影響を与える結果となります。
薄い色合いのネクタイは、テレビ画面では彼の顔色をさらに青白く、疲れて見える効果を生んでしまいました。
また、彼は直前に病気を患っていたこともあり、その健康状態がより視覚的に強調されることとなりました。
ケネディ大統領
一方、ジョン・F・ケネディ大統領は、深みのあるダークスーツに、濃紺のネクタイを選びました。
この選択が彼の若々しさや活力を引き立てる結果となりました。
テレビ画面では、ケネディの装いが彼の健康的な肌色を際立たせ、彼のカリスマ性と堂々とした印象を与える要因となったのです。
パーソナルカラーの視点で見るネクタイ選び
この討論会をパーソナルカラーの視点から考えると、以下のポイントが浮かび上がります
- コントラスト効果
ケネディ大統領が選んだ濃紺のネクタイは、彼の肌や髪の色と強いコントラストを生み出し、彼の顔を鮮明に引き立てました。
当時のテレビは白黒だったため濃紺のネクタイは濃いグレーに表示され、視聴者に力強い印象を与えました。 - 顔色への影響
一方で、ニクソン大統領が選んだ淡い色合いのネクタイは、テレビでは薄いグレーに表示され、彼の青白い顔色を目立たせてしまいました。 - メッセージ性
濃紺や赤といった深みのある色は、見ている人に信頼感や力強さをイメージさせる色です。
ケネディの選択は、彼の自信とエネルギーを強調する効果がありました。
討論会の教訓とその後の影響

この討論会は、視覚的な要素がいかに大きな影響を持つかを政治家や戦略家に示しました。
その後政治の場では、ネクタイやスーツなどの選び方にパーソナルカラーの理論が活用されることが一般化しました。
例えば、ビル・クリントン元大統領やバラク・オバマ元大統領も、場面に応じて強い印象の赤や青などの色を効果的に使い分けることで、信頼感や安定感を視覚的に伝える工夫をしていました。
ニクソン大統領とケネディ大統領のネクタイ選びのエピソードは、パーソナルカラーが印象形成にどれほど影響を与えるかを象徴する出来事です。
自分の特徴に合った色を選ぶことで、健康的で魅力的な印象を与えることができます。
この教訓は、ビジネスシーンや日常生活でも応用できる重要なポイントといえるでしょう。
21世紀:16タイプ診断の登場と多様化
2000年代以降、パーソナルカラー診断はさらに進化を遂げました。
従来の4シーズン分類に加え、それぞれのシーズンをさらに細分化した「16タイプ診断」が登場しました。この方法では、明度や彩度、色相の違いをより細かく分析し、個々に最適な色を提案します。
また、技術の進歩により、オンライン診断やAIを活用した診断サービスも普及しました。
これにより、パーソナルカラー診断はより手軽で身近なものとなり、多くの人が自分の個性に合った色を取り入れられるようになりました。
現在と未来:パーソナルカラーのさらなる進化

現在、パーソナルカラーはファッションやメイクだけでなく、インテリアやブランディングの分野でも活用されています。
色の心理的効果を考慮し、個人の魅力を最大限に引き出すためのツールとしてますます注目を集めています。
今後は、AIやビッグデータを活用した精度の高い診断や、個人のライフスタイルや価値観に基づいた色彩提案が進むことが期待されています。
まとめ
パーソナルカラーの歴史は、美術や色彩学の研究から始まり、100年以上の時間をかけて確立されてきました。
現在では、自己表現や個性を際立たせるための重要なツールとして広く使われています。
クリントン大統領のネクタイ選びの例が示すように、パーソナルカラーは見た目だけでなく、感情や印象に影響を与える強力な手段です。
パーソナルカラーの知識を深めることで、自分に似合う色を見つけ、日々の生活をより豊かに彩ることができるでしょう。
さらに詳しく自分の似合うカラーを知ることでこんなメリットがあります
- 自分の魅力を最大限に引き出す色がわかり自信が持てる
- 新しい自分に出会える
- 化粧品を買うときに色で迷わず買えるようになる
- 服に色物を取り入れられるようになっておしゃれを楽しめる